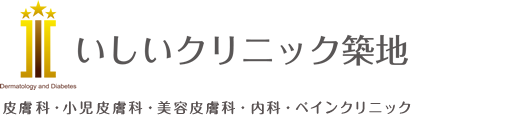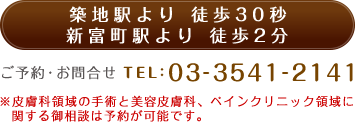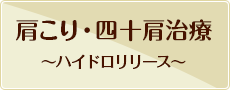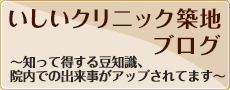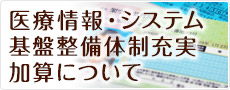尖圭コンジローマとは
尖圭コンジローマ
尖圭コンジローマは性感染症特有の心理的ストレスや不安が伴う疾患です。そのため当院では男性・女性問わず「液体窒素頻回付着療法」や「炭酸ガスレーザー照射療法」を用いることで早期の改善、治癒率の向上に努めております。
尖圭コンジローマの特徴
- ヒトパピローマ(HPV)によって引き起こされる性感染症の一つで性器や肛門周囲などに特徴的なイボが複数できてきます。HPVには複数の型があり尖圭コンジローマを引き起こす型は男女供にHPV6.11型で、女性の子宮頸がんの原因となるHPV16.18.31型とは別のものです。
- 潜伏期間は3週間~8ヶ月です。性器同士が擦れることで粘膜表面の傷から感染します。
- 自然治癒することもありますが、一方で放置して病状が進行するとイボが増殖しサイズも大きくなり治療に長い時間を要します。
尖圭コンジローマの症状
男女共に性器や肛門の周囲に「ニワトリのトサカ」様のできもの、「集族した半米粒サイズ」のできものを認めます。色調は黒褐色のことが多いようです。痛みやかゆみはほぼありません。
尖圭コンジローマの検査項目・検査可能時期
ダーモスコピーと呼ばれる特殊な拡大鏡を用いて診断します。
基本的にその場で診断が可能ですが悩ましい症例も一部あり、その場合は病変の一部を切除し病理検査で診断いたします。病理検査の場合、診断確定には約3週間を要します。
尖圭コンジローマの治療
男性・女性問わず液体窒素頻回付着療法、炭酸ガスレーザー照射療法、ベセルナ軟膏外用療法を組み合わせたコンビネーション治療を各個人の病状に合わせ提案いたします。
炭酸ガスレーザー照射療法
単発もしくは複数の孤立した病変に向いている治療法です。具体的には局所麻酔を行った後に直接病変をレーザーで削り消失を期待するキレの良い治療法です。施術後は歩いて帰宅することが可能です。また基本的には日常生活に極端な制約を要することはありません。
病変が複数ある場合や広い場合は複数日に分けて治療する場合がございます。
病変数や部位によっては施術が困難な場合がございます。
液体窒素頻回付着療法
病変部位に液体窒素を付着する治療法です。この治療法のポイントは’’治療の頻度(回数)’’です。この治療の効果を最大限に出すには2~3日に1回の頻度で治療を受けていただくことが理想なのですが保険診療では1~2週間に1度の施術機会しか許されておりません。そこで当院は自由(自費)診療になりますが十分な治療機会を確保し治癒を目指していく方針で治療を行っております。
ベセルナ軟膏
尖圭コンジローマの治療薬として開発されましたが病変やサイズが大きい病変にはやや効果が乏しい印象のある外用薬です。
尖圭コンジローマの治療費用
※早期の改善、治癒率の向上の観点からコンジローマの治療は自費で行っております。
炭酸ガスレーザー照射療法:¥5,500~(病変の個数や大きさによります)
液体窒素頻回付着療法:¥4,400~
(当て放題 ¥33,000/月:※2~3日に1回施術を受けることが可能です。)
尖圭コンジローマの注意点
- 感染が確認された場合は自分自身だけでなくパートナーも検査する必要があります。
- 一度感染したら抗体ができて生涯感染しないという訳ではありません。
- 尖圭コンジローマはサイズ、個数によっては長期の治療期間を要する場合もございます。また症状が消失した後も数ヶ月経過を観察する必要がある場合もございます。
予防接種について
※予防接種費用助成は医師会加入の医療施設でお受けいただけます。
そのため当院では男性・女性供に接種を行っておりません。
尖圭コンジローマの予防にはワクチンの接種が有効です。
女性は元より、2020年からは男性にも適応が広げられました。
接種時期や費用、注意点は接種を受ける医療施設にご相談ください。
尖圭コンジローマと関係性が深い性感染症
性感染症は複数同時に罹患していることもしばしばで、またそれが無症状であることも少なくありません。そのため当院では尖圭コンジローマと関係性が深い性感染症である「梅毒」「HIV」「B型肝炎」「C型肝炎」の検査もお受けいただけます。
梅毒
梅毒の特徴
胎盤を介して感染する先天梅毒と性感染症の一つである後天梅毒に大別されます。後天梅毒のほとんどは性感染症で細菌が粘膜から侵入することで起こります。2010年頃から増加し始め2022年の感染者数は1万人を超えて社会問題にもなっています。
- 感染者の血液や精液、膣分泌液に菌が含まれており、性行為によりそれらが健常者の皮膚や粘膜に付着することで感染いたします。キスも感染経路となりえます。
- 早期梅毒は多彩な皮膚症状を呈し時期により皮疹の出現と消退を認めることがしばしばです。
- 飛沫感染や空気感染は無いため日常生活で感染することはありません。
- 母子感染は高確率で発生しますので妊娠時には梅毒検査は必須です。
梅毒の症状
潜伏期間は10~90日です。梅毒は4期に分類され感染力の強い第1期と2期を合わせて早期梅毒、それ以降を晩期梅毒と呼びます。皮疹は病期により変化し皮疹が認められない時期もあります(無症状の潜伏梅毒)。
●第一期:感染後90日以内
感染してから3週間程度で感染した部位(性器や口唇、肛門周囲など)にしこりが出現します。これらのしこりは約1ヶ月程度で自然と消えます。この期間は大変感染力が強い時期です。
●第二期:感染後3ヶ月~3年
体幹(梅毒バラ疹)や手のひら・足の裏(梅毒性乾癬)、性器(扁平コンジローマ)に多彩な皮疹を認めます。皮疹は治療をしなくても消失することがあります。この時期に異常を感じる方が多いようです。
●第三期~四期:感染後数年~数十年
皮膚以外の臓器(神経や血管、目)に障害を与える状況となります。
梅毒の検査項目・検査可能時期
採血による抗体チェック(TPHA法とRPR法の組み合わせ)
感染機会の6週間後から検査可能です。
検査結果の見方
TPHA(+) RPR(+)→梅毒に感染しています。
TPHA(-) RPR(-)→梅毒に感染していません。
TPHA(+) RPR(-)→梅毒治療後もしくは梅毒晩期。
TPHA(-) RPR(+)→感染初期もしくは生物学的偽陽性。
検査結果がTPHA(+)RPR(+)な場合は治療を開始する必要があります。また梅毒と診断されれば必ず再度採血を行いTPHAとRPRの実際の数値を測定する定量検査を行うことが必須です(最初に行う検査は感染の有無をチェックする定性検査です。治療効果判定時にはRPRの定量検査値を用います。)
梅毒の治療
抗生剤の内服治療を4~8週間行います。
※当院ではペニシリン注射製剤「ステルイズ」の注射療法は行っておりません。
梅毒の治療経過
まず抗生剤を内服後、2週間で副作用のチェックのために来院していただきます。抗生剤を4週間投与後には再度採血を行いRPRの数値を測定し治療前の数値の半分以下になっていれば治療を終了いたします。数値の低下が悪ければ再度抗生剤の投与を4週間行った後にRPRの数値を測定します。
治療後、約1年間はTP,RPR定量検査の採血フォローが必要です。
梅毒の注意点
- 感染が確認された場合は自分自身だけでなくパートナーも検査する必要があります。
- 感染時期から間もない場合も考慮し(潜伏期間は10~90日)見逃しを防ぐ目的で複数回検査を受けていただく場合もございます。
- 梅毒はHIVに併発する例が増加しております。またHIV以外にも複数の病気に同時に罹患していることが多く、それらが無症状であることも少なくありません。そのため自費となりますが他の性感染症の存在を調べる検査を受けることを強くおすすめいたします。
HIV
<目次>
HIVの特徴
細菌、カビ、ウイルスなどの病原体から人の体を守る免疫細胞に感染するのがHIV(人免疫不全ウイルス)です。しばしばエイズウイルスとも呼ばれます。
エイズとはHIVにより引き起こされる病気のことで、具体的には原因不明の体調不良や下痢、体重減少から悪性腫瘍、様々な感染症などが起こりえます。
感染している人の精液や腟分泌液、血液、母乳が粘膜に接触することで感染します。そのため唾液や尿、汗、涙を介しての感染リスクはありません。
「性行為による感染」「血液感染」「母子感染」がHIVの主な感染経路です。
最近ではピアスや入れ墨など、出血を伴う施術における器具の使い回しで感染に至るケースもあり注意が必要です。
HIVの症状
HIVに感染すると原因不明の体調不良や下痢、体重減少が現れるケースもありますが、一方で無症状な場合もあります。感染初期の上記の様な症状は数日~数ヶ月で多くの場合は自然治癒します。その後は一旦症状がない期間が続きエイズを発症します。発症するまでの期間は1~10年以上と個人差があります。
HIVの検査項目・検査可能時期
採血によるHIV抗原・抗体検査
感染機会の6週間後から検査可能です。
HIVの治療
HIV感染症と診断された全員が治療の対象になります。現代の医学ではHIVウイルスを体内から除去することは出来ませんが、活動を抑えることは可能になってきています。
早期発見・早期治療でエイズの発症を遅らせることが可能になってきています。全国にエイズ治療拠点病院がありますので治療対象者の方には御紹介いたします。
HIVの注意点
- 感染が確認された場合は自分自身だけでなくパートナーも検査する必要があります。
- HIVは早期発見・早期治療が大変重要です。感染機会があった場合は、現状で症状がなくても男女共にまず検査を受けることが大切です。
- 血液検査で調べることができるのでB型肝炎やC型肝炎、梅毒とあわせて検査することをおすすめします。
B型肝炎
<目次>
B型肝炎の特徴
B型肝炎ウイルス(HBV)とよばれる病原体による感染症です。日本国内には約150万人程度の感染者がいると言われており無症状の方も多い(症状が出現するのは20~30%)一方で、肝硬変や肝臓癌を発症する方もいます。
- 無症状の方も多いため自分が感染していることに気が付かずパートナーや家族にうつしてしまう恐れがあります。
- 感染している人の精液や腟分泌液、血液、母乳が粘膜に接触することで感染します。そのため唾液や尿、汗、涙を介しての感染リスクはありません。
- 「性行為による感染」「血液感染」「母子感染」がHBVの主な感染経路です。
- 最近ではピアスや入れ墨など、出血を伴う施術における器具の使い回しで感染に至るケースもあり注意が必要です。
B型肝炎の症状
急性肝炎と慢性肝炎に分けられます。急性肝炎の場合は発熱・食欲不振・体重減少・倦怠感・黄疸などの症状が認められる時期がありますがそれらは自然に治癒することもあります。慢性肝炎の場合は目立った症状はほとんど無く気がついたら肝硬変や肝癌を発症していたということが多いようです。
B型肝炎の検査方法・検査可能時期
採血によるHBs抗原検査を行います。
検査可能時期は感染時期から4~8週後からお願いしております。
B型肝炎の治療
採血によるHBs抗原検査で陽性の方には専門医療機関を御紹介いたします。
B型肝炎の注意点
- B型肝炎ウイルスの感染を予防するにはワクチン接種が有効です。医療従事者や救急救命士、ご家族にB型肝炎の方がいらっしゃる方は御検討ください。
- 感染が確認された場合は自分自身だけでなくパートナーも検査する必要があります。
- B型肝炎は早期発見・早期治療が大変重要です。感染機会があった場合は、現状で症状がなくても男女共にまず検査を受けることが大切です。
- 血液検査で調べることができるのでC型肝炎やHIV、梅毒とあわせて検査することをおすすめします。
C型肝炎
<目次>
C型肝炎の特徴
C型肝炎ウイルス(HBV)とよばれる病原体による感染症です。C型肝炎ウイルスは感染力が弱いため、性交渉による感染リスクはほぼないといわれており性感染症には含まれないかもしれませんが以下に要点を記載いたします。
日本国内には約100万人程度の感染者がいると言われており無症状の方が多い(約80%)一方で、肝硬変や肝臓癌を発症する方もいます。
- 血液感染が主な感染経路です。
- C型肝炎ウイルスは感染力が弱いため、性交渉による感染リスクはほぼないといわれています。しかし、出血を伴うような性交渉がある場合には、血液を介して感染する危険性が高くなります。
- 母子感染のリスクも低いと報告されています。
- 最近ではピアスや入れ墨など、出血を伴う施術における器具の使い回しで感染に至るケースもあり注意が必要です。
C型肝炎の症状
当初は特に症状を認めず、肝硬変や肝癌を発症して気がつく例もあります。
C型肝炎の検査項目・検査可能時期
採血によるHCV抗体検査を行います。
検査可能時期に関しては感染時期から6~8週後からお願いしております。
C型肝炎の治療
採血によるHCV抗体検査で陽性の方には専門医療機関を御紹介いたします。
C型肝炎の注意点
- 現在C型肝炎を予防するワクチンはありません。
- 感染が確認された場合は自分自身だけでなくパートナーも検査する必要があります。
- C型肝炎は早期発見・早期治療が大変重要です。感染機会があった場合は、現状で症状がなくても男女共にまず検査を受けることが大切です。
- 血液検査で調べることができるのでB型肝炎やHIV、梅毒とあわせて検査することをおすすめします。
料金表
通常検査(自費診療)
(税込)
| 検査項目 | 検査方法 | 費用 | 検査結果通知 | 検査可能時期 |
|---|---|---|---|---|
| 梅毒 | 血液 | ¥4,400 | 2~3日後 | 6週間後 |
| HIV抗原・抗体検査(第四世代) | 血液 | ¥4,400 | 2~3日後 | 4週間後 |
| B型肝炎(HBs抗原) | 血液 | ¥4,400 | 2~3日後 | 4~8週後 |
| C型肝炎(HCV抗体) | 血液 | ¥4,400 | 4~10日後 | 6~8週後 |
※初診料・再診療は含まれた金額になります
※相談のみで検査をされない場合は初診料2,200円、再診療1,100円かかります
※検査時期とは感染してから検査可能になる必要時間のことです
※再検査になると結果が遅れる可能性があります
※祝祭日、休診日を挟むと結果が遅れる可能性があります
- 尖圭コンジローマは病変の状況により価格が異なるため要相談となります。